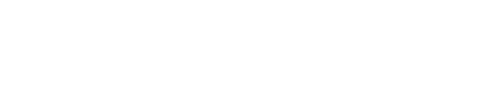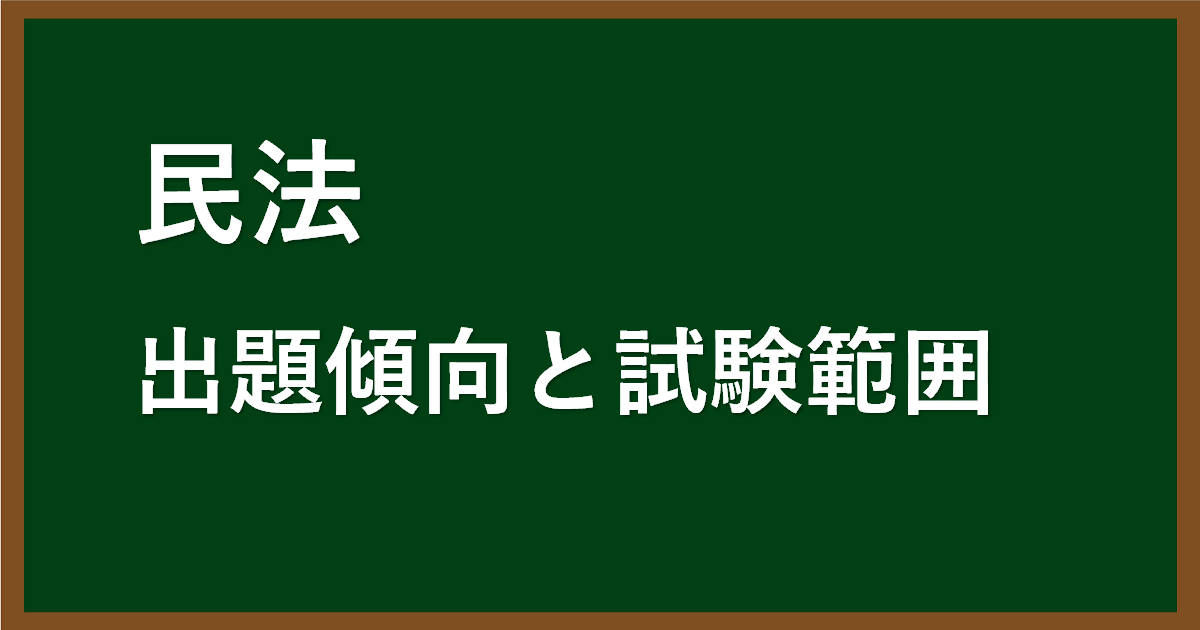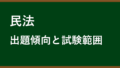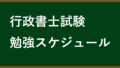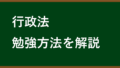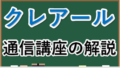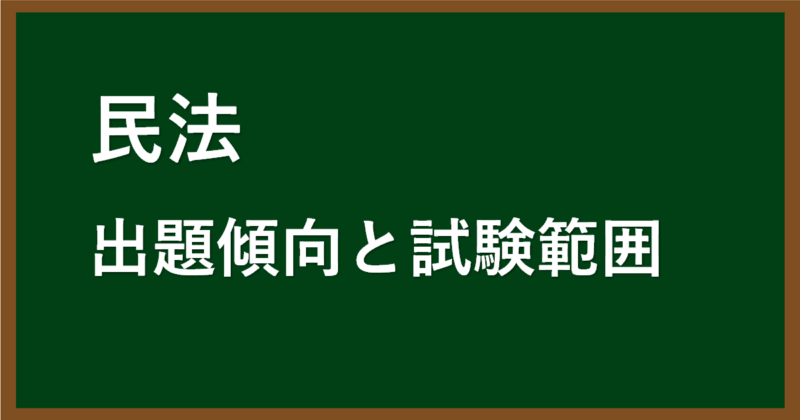
行政書士試験における民法の出題傾向と試験範囲について解説しています。
また、行政書士試験における民法の配点や全体から見た割合、過去の試験問題から見る重要論点なども解説しています。
勉強前に読みたい1冊
行政書士試験は「60点」で合格できる試験です。行政法・民法・憲法・商法・会社法・一般知識と試験範囲は広いですが、全てを完璧に覚える必要はありません。試験勉強を始める前に「どうすれば試験に合格するのか?」「効率的に勉強する為には何を勉強すればいいのか?」など、手当たり次第に勉強するのではなく、ある程度の目印を見つけて勉強することが効率よく合格する近道です。
そんな「効率のいい最短勉強法」のノウハウが書かれている「非常識合格法の書籍」がクレアールの無料資料請求をすると「タダでもらえます」。参考に「する・しない」また、参考に「なる・ならない」は人それぞれだと思いますが、無料でもらえますので1度勉強前に読んでみて損はないと思います。
行政書士「民法」の配点と割合
民法の配点と割合は次のようになっています。(試験年度により多少の前後はあります)
5肢択一式:40問中9問(36点)
多肢選択式:3問中、出題なし(0点)
記述式:3問中2問(40点)
関連記事:「記述式対策!予想問題集を使って部分点を狙う方法」
民法のみでの配点は合計で76点あり、試験全体の約25.3%を占めています。行政書士試験は60%を得点できれば合格する試験ですから、民法の占める割合はかなり高いと言えます。
行政書士「民法」の出題傾向
近年の行政書士試験における民法の出題傾向としては、次の2点があげられます。
事例形式の問題が多い
行政法は条文に書いてあることを「そのまま」聞いてくる問題が多いのに対して、民法では「事例形式」の問題が多い傾向にあります。
関連記事:「行政法の勉強法は過去問と記述問題集を解くだけ!」
Aが自己の所有する甲土地をBと通謀してBに売却(仮装売買)した場合に関する次のア~オの記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当でないものの組合せはどれか。
ア:Bが甲土地をAに無断でCに転売した場合に、善意のCは、A・B間の売買の無効を主張して、B・C間の売買を解消することができる。
イ:Bが甲土地をAに無断でCに転売した場合に、善意のCに対して、AはA・B間の売買の無効を対抗することはできないが、Bはこれを対抗することができる。
※ウ~オは省略
上記のように「Aさん・Bさん・Cさん」を登場させ、具体的な場面を設定して答えを聞いてくる形式の問題が事例形式という問題です。勉強を始めると分かりますが、上記の問題は94条の虚偽表示(通謀虚偽表示)に関する問題です。
第94条(虚偽表示)
1項:相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
2項:前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
条文をそのまま聞いてくる問題であれば、上記の第94条の条文を覚えていれば正解できます。(行政法では条文を覚えていれば正解できる問題も多い)しかし、事例形式の問題を正解するには、条文の暗記だけでは足りません。暗記した条文を問題に当てはめて考える必要があります。
実際に当てはめてみると、1項の「相手方と通じてした虚偽の意思表示」というのは、「AさんとBさんの間の仮装売買」のことであり、2項の「善意の第三者」というのは「Cさん」のことです。
①上記の問題を読んだ時に、虚偽表示の問題だと気付いて、条文や判例を思い出すこと。
②思い出した条文や判例を問題に当てはめる思考力。
この2つが問題に正解するカギになります。これには条文や判例を覚えることはもちろん、過去問などを通して日頃から事例を当てはめる練習を繰り返し行う必要があります。
債権分野からの出題が多い
民法を勉強する際の中心は「総則・物権・債権」ですが、その中でも「債権」からの出題が目立ちます。5肢択一式・記述式ともに債権分野から出題される割合が高いので、債権➡物権➡総論➡余力があれば家族。の順番でウエイトを置いて勉強するのが合格への近道です。
| 試験年度 | 5肢択一(民法9問) | 記述(民法2問) |
| 2018年度 | 債権:9問中3問 | 債権:2問中1問 |
| 2017年度 | 債権:9問中4問 | 債権:2問中2問 |
| 2016年度 | 債権:9問中3問 | 債権:2問中1問 |
| 2015年度 | 債権:9問中4問 | 債権:2問中0問 |
| 2014年度 | 債権:9問中5問 | 債権:2問中2問 |
| 2013年度 | 債権:9問中5問 | 債権:2問中0問 |
| 2012年度 | 債権:9問中4問 | 債権:2問中1問 |
| 2011年度 | 債権:9問中4問 | 債権:2問中1問 |
| 2010年度 | 債権:9問中3問 | 債権:2問中2問 |
行政書士「民法」の試験範囲と重要論点
行政書士試験での民法の試験範囲と重要論点は次の通りです。
- 【民法総則】
- 序論
- 人(権利の主体)➡重要論点
- 法人(権利の主体)
- 物
- 法律行為
- 意思表示➡重要論点
- 代理➡重要論点
- 無効・取消し➡重要論点
- 条件・期限
- 時効➡重要論点
- 【物権】
- 物権総説
- 物権変動(総論)
- 不動産物権変動➡重要論点
- 動産物権変動➡重要論点
- 占有権➡重要論点
- 所有権➡重要論点
- 用益物権(地上権・永小作権・地役権)
- 【担保物権】
- 担保物権総論
- 留置権➡重要論点
- 先取特権
- 質権
- 抵当権➡重要論点
- 非典型担保
- 【債権総論】
- 債権の意義と目的
- 債務不履行➡重要論点
- 責任財産の保全➡重要論点
- 多数当事者の債権・債務関係➡重要論点
- 債権譲渡と債権引受➡重要論点
- 債権の消滅➡重要論点
- 【債権各論】
- 契約総論
- 贈与➡重要論点
- 売買➡重要論点
- 消費貸借・使用貸借
- 賃貸借➡重要論点
- 請負➡重要論点
- その他の契約
- 不法行為
- 【親族】
- 親族法総論
- 総則(親族)
- 婚姻・離婚
- 親子
- 【相続】
- 総則
- 相続人
- 相続の効力
- 相続の承認・放棄
- 遺言
- 遺留分
まとめ
民法を勉強する場合、債権・物権・総則を中心に、それぞれ条文の原則と例外・要件や判例などをまずは暗記しましょう。民法は過去問を解くだけでは完璧に仕上がりませんが、まずは過去問が解けなければ話になりません。暗記の後は過去問に挑戦して、しっかりと事例を条文等に落とし込む力を付けてください。