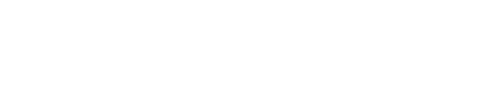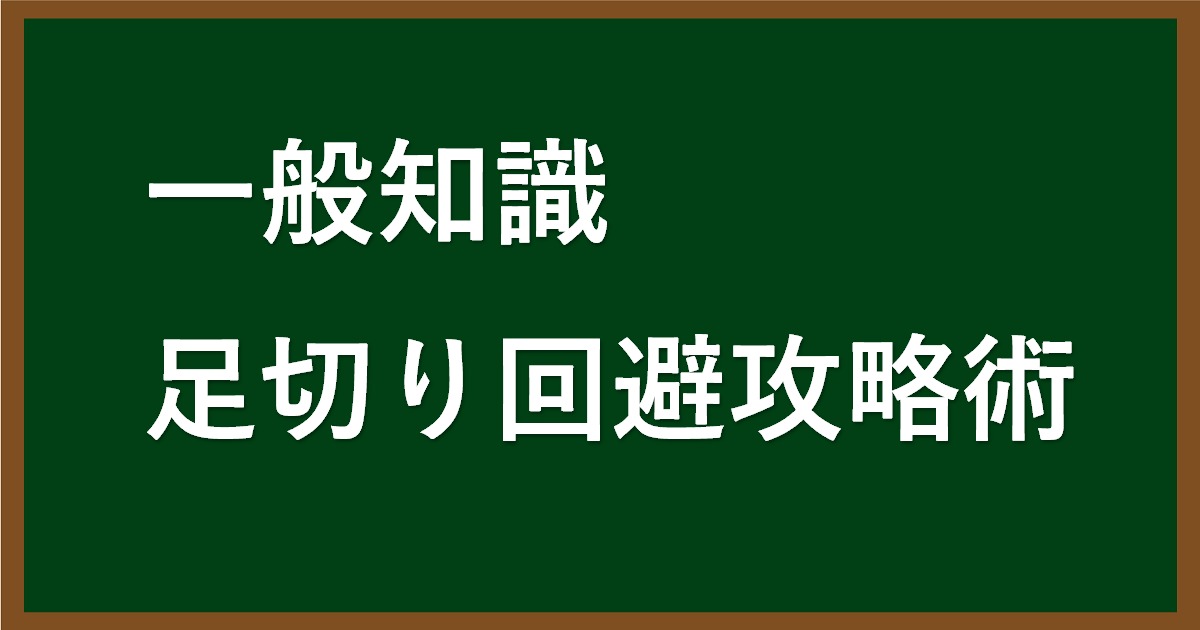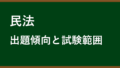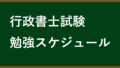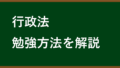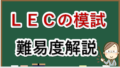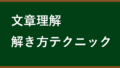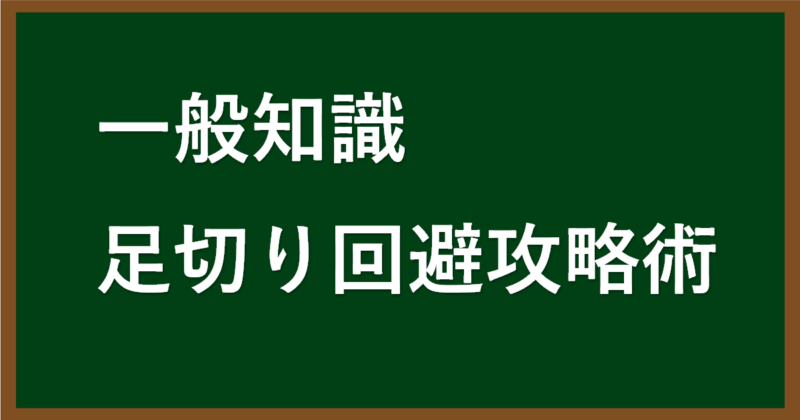
行政書士試験の受験者が、試験当日まで心配・不安に思う事の1つに、「一般知識の足切りに引っかからないか?」があると思います。実際に私もずっと不安でした。
この不安は、試験勉強に本気で取り組んだ方ほど増すと思います。なぜなら、一般知識で6問正解しなければ、費やした時間と苦労が水の泡になると分かっているからです。
そんな不安を少しでも解消できるよう、私が実践した足切り回避の為の勉強方法をご紹介します。
勉強前に読みたい1冊
行政書士試験は「60点」で合格できる試験です。行政法・民法・憲法・商法・会社法・一般知識と試験範囲は広いですが、全てを完璧に覚える必要はありません。試験勉強を始める前に「どうすれば試験に合格するのか?」「効率的に勉強する為には何を勉強すればいいのか?」など、手当たり次第に勉強するのではなく、ある程度の目印を見つけて勉強することが効率よく合格する近道です。
そんな「効率のいい最短勉強法」のノウハウが書かれている「非常識合格法の書籍」がクレアールの無料資料請求をすると「タダでもらえます」。参考に「する・しない」また、参考に「なる・ならない」は人それぞれだと思いますが、無料でもらえますので1度勉強前に読んでみて損はないと思います。
一般知識の問題数と得点配分
まずは基本情報として、一般知識の問題数と得点配分を確認してみましょう。
| 科目 | 問題数 | 点数 |
| 政治・経済・社会 | 8問 | 32点 |
| 個人情報保護法・情報通信 | 3問 | 12点 |
| 文章理解 | 3問 | 12点 |
| 合計 | 14問 | 56点 |
※問題数は2018年度の試験問題のデータです。
ご存知だとは思いますが、一般知識は6問(24点)以上の正解で足切り回避となります。
足切り回避の為のポイント
結論から言うと、一般知識の足切りを確実に回避する為には、文章理解と個人情報保護法にかかっています。
| 科目 | 問題数 | 目標正解数 |
| 政治・経済・社会 | 8問 | 1問以上 |
| 個人情報保護法・情報通信 | 3問 | 2問 |
| 文章理解 | 3問 | 3問 |
目標は、政治・経済・社会以外で4問~5問正解することです。最近の行政書士試験の政治・経済・社会の問題を見ると、事前の対策はかなり難しい問題となっています。
実際に、私は2018年度の試験を受けるに当たり、政治・経済・社会の勉強をLECのテキストをベースに「100時間程度」時間を使い今日しましたが、本試験の問題では全く役に立ちませんでした。
逆に、LECのテキストをベースに勉強した「個人情報保護法」と「文章理解の解き方テクニック」は役に立ち、無事足切り回避することができました。
文章理解はこの3パターン!
文章理解の問題は、大きく分けて以下の3タイプがあります。
文章理解の問題を解く為には、「コツ」を意識しながら過去問の文章問題や、市販の問題集の文章問題を複数解いてみることです。1日に解く問題は2~3問でかまいません。大事なのは「毎日継続」して1ヵ月程度続けることです。最初は難しくても、続けている間に不思議と解けるようになります。
私も最初に過去問の文章理解の問題を解いた時は、全く正解しませんでした。しかし、毎日「コツ」を意識しながら2~3問解いていると、1ヵ月ぐらいで正解できるようになりました。
要旨把握型
近年の行政書士試験の文章理解の問題は、次で説明する「並べ替え型」と「空欄補充型」の問題が多いのですが、この「要旨把握型」も出題されることがありますので、解説していきます。
「要旨把握型」とは、筆者の中心的な主張を文章から読み取る事ができるかを問う問題です。問題の出し方としては、次のような問題があります。
- ア~オの記述のうち、本文の趣旨と合うものの組合せとして、妥当なものはどれか。(本文の趣旨を読み取れるかがポイント)
- ア~オの記述のうち、本文の趣旨に合っていないものの組合せはどれか。
- 次の1~5の記述のうち、本文の内容と一致しているものはどれか。
「本文の趣旨」や「本文の内容」と言葉は違いますが、要は筆者の主張がポイントで、あとは筆者の主張と合う選択肢を選ぶ問題か、筆者の主張と合わない選択肢を選ぶ問題かの違いです。
- 文章の中で繰り返し出てくる言葉に注目する
- 文章の最後に書いてある引用出典名(タイトル)を見る
- 接続詞に注目する
- 段落ごとに分けて考える
文章理解のコツを「もう少し詳しく解説」
並べ替え型
「並べ替え型」とは、言葉の通り、2~3行程度の文章が4~5つ書いてあり、その文章を正しい順番に並べることを求める問題です。問題の出し方としては、次のような問題があります。
- 本文の後に続く文章を、ア~オの記述を並べ替えて作る場合、順序として適切なものはどれか。
- 本文中の空欄に入る文章をア~エの文を並べ替えて作る場合、順序として適当なものはどれか。
並べ替えの問題を解くコツは、①先頭にくる文を検討する②一度に並べ替えようとせず、選択肢をグループ化するの2点です。
- 頭に接続語や指示語がくる文は、先頭には来ない可能性が高い。
- キーワードに着目する。
- 指示語とその指示内容に着目する。
- 接続語に着目して、文の流れを考える
文章理解のコツを「もう少し詳しく解説」
空欄補充型
「空欄補充型」とは、文章中の空欄に適切な語句を入れて、正しい文章を完成させることを問う問題です。問題の出し方としては、次のような問題があります。
- 本文中の空欄ア~エに当てはまる語句の組合せとして、正しいものはどれか。
- 次のア~カの記述のうち、本文の空欄A・Bに当てはまるものの組合せとして適当なものはどれか。
- 本文中の空欄に入る言葉として適当なものはどれか。
行政書士試験の空欄補充問題は、複数の空欄にそれぞれ違う語句を入れ、正しい文章を完成させる問題が多いです。
- 文章全体の要旨をおおまかに把握すること
- 空欄の前後の語句や表現に注目すること
- 最後に文章を通読して矛盾点がないかを確認する
文章理解のコツを「もう少し詳しく解説」
個人情報保護法は暗記で解ける!
行政書士試験の一般知識科目で、唯一出題範囲が決まっているのが個人情報保護法関連の問題です。政治・経済・社会は範囲の特定が不可能ですし、文章理解の問題は暗記では解けません。
それに比べて個人情報保護法関連の問題は、行政法科目などと同じように、法律がありその中から出題される為、暗記さえしていれば正解数を稼ぐことができます。
しかも難易度が高い問題はあまり無く、重要条文から順番に覚えていけば正解に近づくので、短期間でも正解に結び付く科目だと言えると思います。
個人情報保護法関連で重要な法律は以下の4つです。
個人情報保護法
個人情報保護法は、行政機関や民間の企業などで取り扱われるこ「個人情報の保護」に関する「基本法」としての部分と、民間の企業などを対象とする「一般法」としての部分に分かれます。
個人情報保護法を勉強する上でのポイントは、2015年・2016年の法改正部分を中心に勉強することです。また、目的条文は重要ですから覚えるようにしてください。
行政機関個人情報保護法
行政機関個人情報保護法は、紙ベースの個人情報を含めた、「国の行政機関」に対しての個人情報の取り扱いに関するルールを定めた法律です。
注意点は「国の行政機関」という箇所で、「地方公共団体」や「独立行政法人」などは対象としていません。(地方公共団体や独立行政法人を対象とした法律は別であります)
勉強する上でのポイントは個人情報保護法と同じです。2015年・2016年の改正部分を中心に、目的条文なども暗記するとよいでしょう。
行政機関情報公開法
行政機関情報公開法は、行政機関が保有する「行政文書」を、国民の側から情報公開を求める場合のルールを決めている法律です。
行政機関情報公開法も行政機関個人情報と同じく、「国の機関」を対象としています。(過去の行政書士試験問題でも出た事があります※2017年・問57の2)
勉強する上でのポイントは、行政文書の開示請求の方法や、開示請求ができる人(「何人も」となっているので、個人・法人・外国人も請求可能)、「不開示情報」の取り扱いなどを中心に勉強するとよいでしょう。
公文書管理法
公文書管理法は、行政機関が保有する「文書」を、適切に管理する規律を定めた法律です。「文書」には現用文書(行政機関が業務で使用中の文書)と、非現用文書(使用を終えた文書)の2種類があります。
勉強する上でのポイントは、目的条文や対象となる機関等、管理の対象となる「文書」などを中心に勉強するとよいでしょう。
科目別の勉強方法
関連記事:「記述式対策!予想問題集を使って部分点を狙う方法」
関連記事:「行政法の勉強法は過去問と記述問題集を解くだけ!」
関連記事:「民法の出題傾向と試験範囲を徹底分析!」
行政書士の講座解説
行政書士試験の勉強を独学ではなく、資格スクールで検討中の方向けの当サイト解説記事です。よろしければご活用ください。
まとめ
行政書士試験の一般知識攻略のコツをご説明してきましたが、いかがでしたでしょうか。
文章理解問題は、ある程度の「慣れ」が必要ですから、本試験の3ヵ月前ぐらいからの準備をお勧めします。個人情報保護法は暗記すれば正解できる問題がほとんどですから、試験の直前期でも十分間に合うと思います。