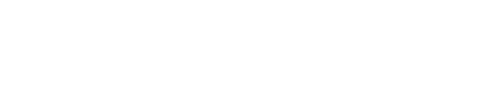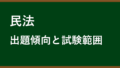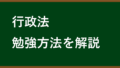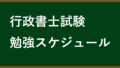行政書士試験合格までの勉強時間について、「独学」「通学」「科目別」に分けて解説しています。また、他資格との比較も紹介していますので参考にして下さい。
※ここで紹介している「勉強時間」は、200点以上のラクラク合格を基準にしています。180点のギリギリ合格の場合は、100~200時間減らした勉強時間での合格も十分可能だと考えています。
独学での勉強時間
【独学+法律知識なし】
勉強時間の目安は「800~1,000時間」です。
法律知識とは、民法・憲法・会社法(商法含む)のことで、大学の法学部出身者の方などは一通り勉強している科目です。また、宅建の勉強をした方は、民法を少し勉強したと思います。
法律知識なしの独学は、勉強を始めた2~3ヵ月は苦戦すると思います。勉強の初めは、民法や行政法など個別の「解説本」で少しづつ理解を深めましょう。
【独学+法律知識多少あり】
勉強時間の目安は「600~700時間」です。
独学でも、事前の法律知識が多少ある方であれば、そこまで難しい内容ではありません。
ただし、行政法関係については過去に勉強経験があるという方は少ないと思います。ですから、行政法関係については一から勉強をする必要があります。
通学での勉強時間
【通学+法律知識なし】
勉強時間の目安は「600~700時間」です。
法律知識とは、民法・憲法・会社法(商法含む)のことで、大学の法学部出身者の方などは一通り勉強している科目です。また、宅建の勉強をした方は、民法を少し勉強したと思います。
通学の場合は事前の法律知識が無くても、「テキストが分かり易い」や「不明点は講師に聞く」などの利点がある為、理解できずに勉強が進まないという事は少ないと思います。
学校のテキスト+過去問などを繰り返し勉強すれば、どなたでも合格できる試験内容だと思います。
【通学+法律知識多少あり】
勉強時間の目安は「500時間程度」です。
以前の法律知識がしっかりある方なら、もっと少ない勉強時間での合格もあり得ます。ちなみに私は通学+法律知識多少ありでしたが、絶対に1年で合格する必要があったので、1,000時間程度は勉強しました。
科目別の勉強時間
【800時間勉強すると仮定した場合】
| 行政法 | 400時間程度 |
| 民法 | 250時間程度 |
| 憲法 | 100時間程度 |
| 商法・会社法 | 50時間程度 |
| 一般知識 | 100時間程度 |
行政書士試験の最重要科目は「行政法」です。
行政法は条文を暗記すれば解ける問題も多く、勉強時間をかければ素直に得点が稼げる科目です。しかも、試験科目の中で最も配点が多いので、行政法には十分な勉強時間を確保してください。
関連記事:「行政法の勉強法は過去問と記述問題集を解くだけ!」
関連記事:「記述式対策!予想問題集を使って部分点を狙う方法」
民法は2番目に重要な科目で、行政法の次に配点が多いです。民法は範囲が広く、また、問題の内容も横断知識や応用力が必要な為、結構難しい内容だと思います。
「代理」「物権」「債権者代位権」「詐害行為取消権」「債務不履行」などなど、過去の頻出テーマを重点的に勉強することが重要です。
関連記事:「民法の出題傾向と試験範囲を徹底分析!」
一般知識については、「個人情報保護法と文章理解」で足切りを回避する事だけを考えましょう。個人情報保護法は条文暗記で解けます。文章理解は、解き方の「コツ」さえ勉強すれば、3問中2問ぐらいは簡単に正解できるようになります。
政治・経済・社会分野については、勉強したからといって正解できる問題ではありませんから、あまり深追いする必要はありません。
憲法は基礎法学も含めて、7問中3~4問程度を正解できればOKです。
商法・会社法は5問中1~2問程度の正解でOKです。
他資格との比較
参考までに、他資格との勉強時間の比較一覧を紹介します。
(詳しくは「社労士と行政書士の難易度比較」をご覧ください。)
(詳しくは「宅建と行政書士の難易度比較」をご覧ください。)
| 資格名 | 勉強時間 |
| 行政書士 | 500~800時間 |
| 宅地建物取引士 | 300時間前後 |
| 社会保険労務士 | 800~1000時間前後 |
| 司法書士 | 3,000時間前後 |
| マンション管理士 | 400時間前後 |
| 管理業務主任者 | 300時間前後 |
まとめ
行政書士の勉強時間について解説をしてきましたが、いかがでしたでしょうか。
根気よく勉強する事は結構難しいですが、これさえできれば、行政書士試験はどなたでも合格できる試験だと思っています。
ぜひ隙間時間なども活用して、行政書士資格の取得を目指してみて下さい!